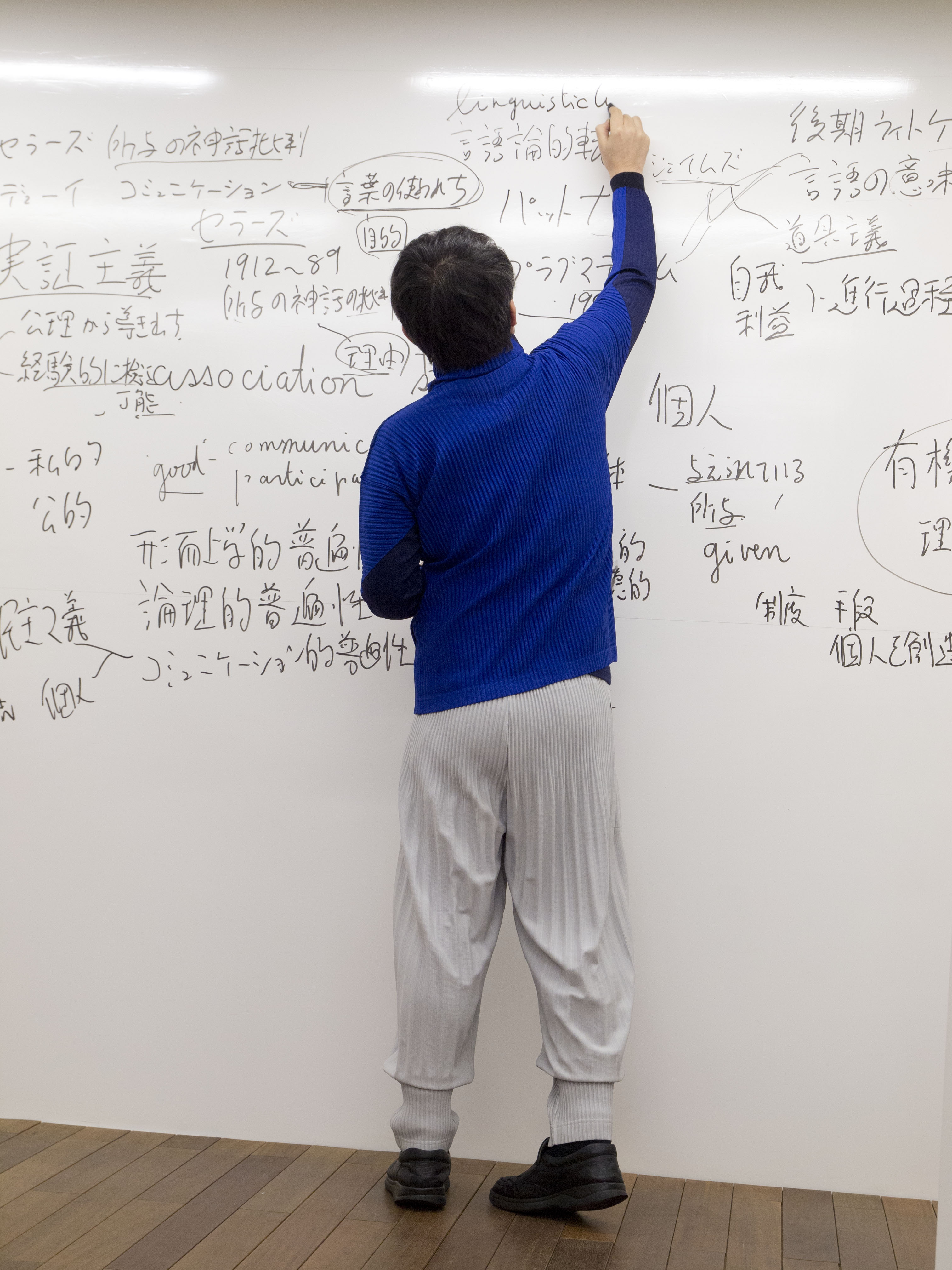![]()
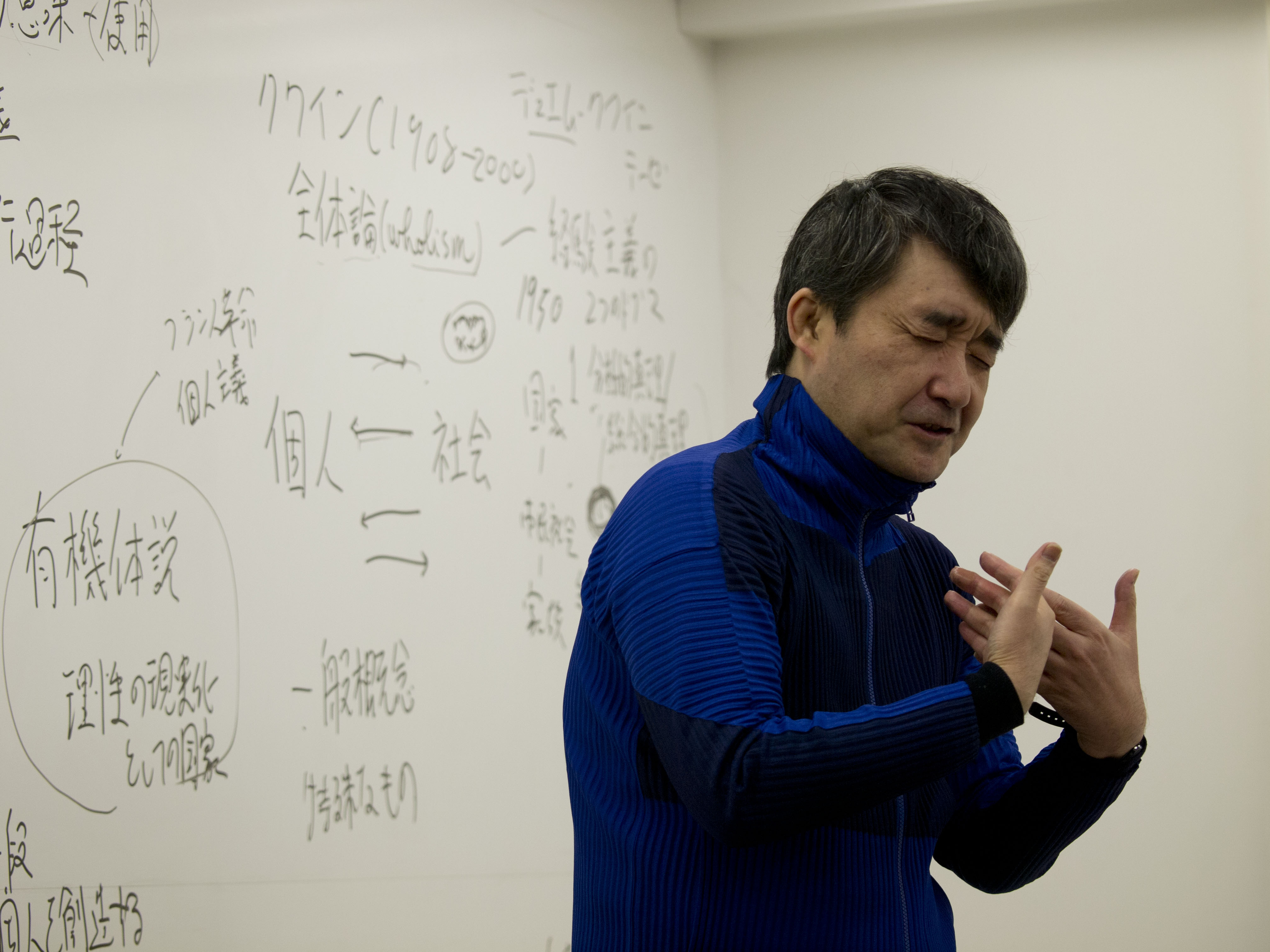
カフカ(一八八三-一九二四)の長編小説『審判 Der Process』(一九二五)、そして、この中で作中作として語られる「掟の門前 Vor dem Gesetz」は、「法」の本質の不可解さ、あるいは理不尽さを象徴する作品として知られている。
法律をあまり意識しないで生きている一般人のイメージでは、「法」は予め決まったプログラム通りにルール違反かどうか判定し、違反者に強制措置を科す、自動的に動く機械のような存在で、法律家や警官はそのエージェント――『マトリックス』のエージェント・スミスのような意味で――だろう。ルールに違反したら、怖い目に遭うが、違反しなかったら、何もして来ないので、無視していい存在という感じだろう。
『審判』のヨーゼフ・K(銀行員)が遭遇する「法」はそれとは少し違っている。何かの「機械」のようなものが作動していて、彼がそれによって動きを封じられていくので、その点では、普通の人の抱く「法」のイメージに近い。しかし、彼は自分が「何をした」のか分からないまま、突然下宿で二人の男たちの訪問を受け、「あなたは逮捕された」、と告げられる。彼らは、Kを監督官と呼ばれる男のところに連れて行き、同じ下宿の隣人を巻き込むなど、彼のプライヴェートをかき乱す。しかし、彼はどこかに強制連行されたわけではなかった。しかし、二人と、彼らに協力しているように見える銀行の同僚に絶えず監視され、裁判所から呼び出しを受けることになる。
しかし、裁判所らしきところを訪れても、どの法廷が彼の訴訟を担当しているのか、どういう容疑で「逮捕」されたのか、これから何をしたらいいのか、誰もはっきりしたことを教えてくれない。田舎からやって来た叔父の勧めで、叔父の友人の弁護士に相談するが、病気がちの弁護士は法律関係の人脈はありそうだが、彼のために何をやってくれているのか分からない――弁護士事務所で、Kは弁護士の愛人らしい女性と関係を持ってしまう。その後、裁判官に強い影響力があるという法廷画家にも相談に行くが、やはり裁判の複雑さを説明されるだけで大きな進展はない。しかし、彼をめぐる「法」の「プロセス」――タイトルの〈der Process〉は、「審判」というよりは、「プロセス(訴訟過程)」という意味だ――は、どんどん進んでいるようだ。最後は、唐突に登場した二人の処刑人による、Kの処刑の場面で終わる。
小説の末尾に近いところで、大聖堂に入ったKは教誨師から「掟の門」の寓話を語られる。田舎から出てきた男が、「掟の門」を通ろうとするが、門の前に番人がいて、入れてくれない。男は門番の機嫌を取ろうとするが、門番によると、この向こうにまたいくつも門があり、その前には、自分よりずっと強く、自分は顔を見ることもできないような門番たちがいる、と告げる。男は、入れてもらえる時を門の前で待ち続けるが、やがて年老い、弱っていく。亡くなる直前、男はどうして他の人間がやって来なかったのか、と門番に聴いた。すると、門番は、それはこの門がお前のためのものだからだ、と告げ、男が息を引き取った後、門を閉める。
『審判』の本筋だけを見ていると、「法」が自分を追い詰めているという妄想に取り憑かれた男の現実と幻影が混じった物語であるように見える。それを前提にしたうえで、「法」とは何の象徴か、文字通りの意味で「法律」か、法曹界か、政治的あるいは経済的権力か、フロイトやラカンの言う意味での象徴的な「父」か、と考えるのが、この小説を解釈する時の定石だろう。多分、それで間違ってはいないだろう。しかし、それだけだと、どうしてそんなに法律が気になるのか、あるいは、どうして「法」が父や社会的権威の象徴になるのか、といった疑問は残る。
そこで補助線として、「掟の門」の寓意を重ね合わせて考えてみよう。「掟の門」は、特定の誰かのために現われるもののようだ。その意味で、「私的 privat」なものである。万人に平等に適用されねばならない「掟=法律Gesetz」が「私的」であるというのは矛盾した話である。ただ、田舎から来た男を、訴えられて訴訟に巻き込まれた人間としてではなく、「法律」を"自分のもの"にしたい、というある意味、万人に共通の欲望に強く突き動かされ、じっとしていられなくなった人間として能動的に捉えると、分かりやすくなるように思える--この点に関連した拙稿として、「法外なもの」とは何か――/仲正昌樹 - SYNODOSを参照。
私たちがこの世界に「掟」が存在することを最初に意識した瞬間を思い出してみよう。自由に行動させてくれないルールは面倒くさい。ルールを他人から押し付けられるのは不快だが、逆に、自分が他人に押し付けることができると、気持ちいい。
幼少期に階段から落ちて歩き方が少々おかしかったということもあって、幼稚園から中学に入る頃までの私は、他の子と同じように動作することができず、親や親せき、先生によく注意される子だった。周りの子まで、大人の真似をして、私が何か外れたことをするたびに、「〇〇してはいけないんだよ!」、と教えようとする。ルールの存在を私に教えてやろうと、いつも待ち構えている子もいたような気がする。それが非常に苦痛であった。
他人の行動を強制によって支配するやり方は、大きく分けて二つある。暴力による威嚇と、言葉による威嚇である。前者は原始的なので、子供でも、お互いの間で実行できる。後者の場合、自分の背後にある権力とか、利害関係をほのめかすなどテクニックが必要だが、一番ストレートに効き目があるのが、「ルールです!」だ。複雑な言い回しはいらない。「ルール」の存在を端的に指摘されたら、抵抗しても無駄である。「ルールです!」で、相手の動きをぴたっと止められると気持ちがいいし、かっこいい。一種の呪文のように思えてくるのかもしれない。
私のように、その呪文でやりこめられる経験を積み重ねると、ルールを適用される側ではなく、適用する側になりたくなる。相手を支配したような気になれそうだ。私のように、ルールによって抑圧されたという経験が多く、トラウマのようになると、かえってルールに固執するようになる。ルールを嫌いながら、同時にルールに魅せられるわけである。
もう少し大きくなると、国家のルールで、どんなにあがいても回避できない「法律」というものが存在することを学ぶ。その場合の法律は、世界を支配する呪文であるルールの大本のルールの一番手強いルールのようなものとしてイメージされるのではないか。門の向こう側の門の前に、次第により強くなる門番たちが立ちはだかっているというのは、そうした"法律"に対する幼児的な怖れの象徴ではないか。
無論、法律家とか警官になろう、と早くから志している子や社会科で公民が好きな子以外は、「法律」を絶えず意識し、早くそれを身に付けて自分の武器にしようなどとは思わないだろう。ほとんどの子供は、「法律=掟」が、自分に直接手をかけてくることは滅多にないとしれば、ひとまず安心し、日常的には"法律"のことなど忘れて過ごすことになるだろう。
しかし、社会の中にはいろんなマナー、クラスや部活、町内会の決まりごと、校則、職場の規則、消費者契約する時の約款など、いろんなローカルなルールがある。それらを身に付け、意識しなくてもルール通りに振る舞える人は、不器用でしょっちゅうルールからはみ出している人間に対して優位に立てる。ネット上のクラスターでも、ルールを口にして"議論"を仕切りたがる人が少なくない。
私は大学院時代は言語哲学と文芸批評が専門だったが、法学部所属の語学教員になったせいで、当初はしょっちゅう、同僚から「法律では...」、と解説され、不快だった。私より大分年下の同僚が親切そうに、「法律では...」、と言って来る。法学部(法学類)に務めて既に二十四年も経ち、法哲学・法思想史や医事法関係の研究もそれなりにやって、論文も書いているのだが、時々、二年くらい前に法学を勉強し始めたばかりの"法学者の卵"に、「法律では...」を聞かされることがある。
銀行員という、法律と結構縁がある職業に就いているKが、様々な場面で、「掟」の呪文によって支配されている、という気分になっていてもおかしくない。個人として、あるいは銀行として訴えられることもしばしばある、と考えられる――作者カフカは、法学を学び、司法研修を受けているが、弁護士になることなく、保険会社に就職する。
職業的法律家ではない普通の人間は、かなり理不尽な言いがかりでも、「訴えてやる。お前を法廷に引きずり出すぞ」、と言われただけで、動揺する。どこかに、それをもっともらしい訴状に仕立てあげる悪徳弁護士がいるかもしれないし、それと癒着する腐った裁判官がいないとも限らない。
そうした「法」を取り巻く不確実性に由来する不安が、Kの一連の妄想を生み出したのかもしれない。「法律=掟」は絶対的な強制力を持つ(ように素人には見える)。しかし、その解釈と適用は、法律家同士の専門的なやりとり次第で、どう転ぶか分からない(ように素人には見える)。その意味で、「法」は絶対的に公的(öffentlich)であると同時に、私秘的(privat)である――〈privat〉には、「個人的」、「親密な」、という意味の他に、関係者以外には「秘密にされる」という意味もある。
銀行の業務に関係する法律、更には、親戚との関係や性道徳など、様々な社会的なルールに煩わされてきたであろうKは、何らかの形で公的に「訴えられた」ことで、「法」それ自体と向き合わざるを得なくなった(ように感じた)。そのことによって、彼の内なる「法」に対する両義的な感情が刺激され、「法」に一方的に支配されるのではなく、「法」の本質を知り、「法」を呪文のように操ることのできる側に回りたい、「法」によって世界を支配する側に回りたいという、最も恐るべき欲望をはっきりと抱くようになったと考えると、物語が展開していく論理がかなり見通しやすくなる。Kは、世界の秘密のカギを解く呪文として使える「法」を探し始める。それに伴って、性的欲望やサド・マゾヒズム的な欲望、のしあがりたいという権力欲等、彼の内の様々な欲望を抑圧してきた諸々のルール(「法」の分身)が露わになっていく。
しかし、様々のルールを束ねる、究極の「法」という表象は、大いなるデコイである。脱構築的な文芸批評でしばしば指摘されるように、あるいは、ドゥルーズ+ガタリが『アンチ・オイディプス』で、「エディプス・コンプレックス」に関して指摘したように、「禁止(禁忌)」の札を貼り付けること、門から入られないようにすることは、「禁止されているもの」は、自分が欲しているものだという錯覚を抱かせる。無論、本当に錯覚なのか、潜在的な欲望が顕在化されるだけなのか、本当のところは分からないが、少なくとも、禁止が強力であればあるほど、その向こうにあるものに関心が集中し、欲望の焦点になりやすいのは確かである。
ヨーゼフ・Kは、自分の目の前に「掟の門」を見てしまい、呪縛されていった。自分を至るところで支配していた「法」のネットワーク(網の目)が、目に見えるようになった。それに抗おうとすると、「法」は蜘の網のように、ますます強く彼の身体に絡みついてくる。「掟の門」とその向こうにある「法」の本体は幻想かもしれないが、彼の行動に対する、法のリアクションはリアルである。
会社、学校、コンビニ、列車やバスの中、役所や議会などで、法が恣意的に運用されていて、ルールをないがしろにしている人や、勝手にルールを解釈して傍若無人に振る舞う人が気になり始め、「法」に寄生する彼らに抗議しようとすると、自分の方が無茶なクレーマーになり、「法」によって取り締まられることになる。和解とか少額の損害賠償で済む訴訟で徹底的に争い、自分の方から相手や裁判所、国家、更には、「法」それ自体の嘘を暴き立てるべく争おうとすると、危ない訴訟マニアになる。正義のために闘う自分が抑え付けられることに反発し、行動がエスカレートすると、狂人扱いされ、「法」の共同体を構成する正規のメンバーと認められなくなる。
「法」はそうやって、「掟の門」を見てしまった者自身の行動を利用して、その「力」を発揮し、支配圏を拡大していく。紙に書かれた法の条文が、現実化していく。デリダなどの現代思想家が、カフカの作品にインスピレーションを得て「法の力」と呼ぶのは、こうした「デコイ」を介して、Kのような人物を巻き込み、自己をネットワーク状に実体化していく力、物心ついた時から私たちに取り憑いている「禁止」の力である。