![]()
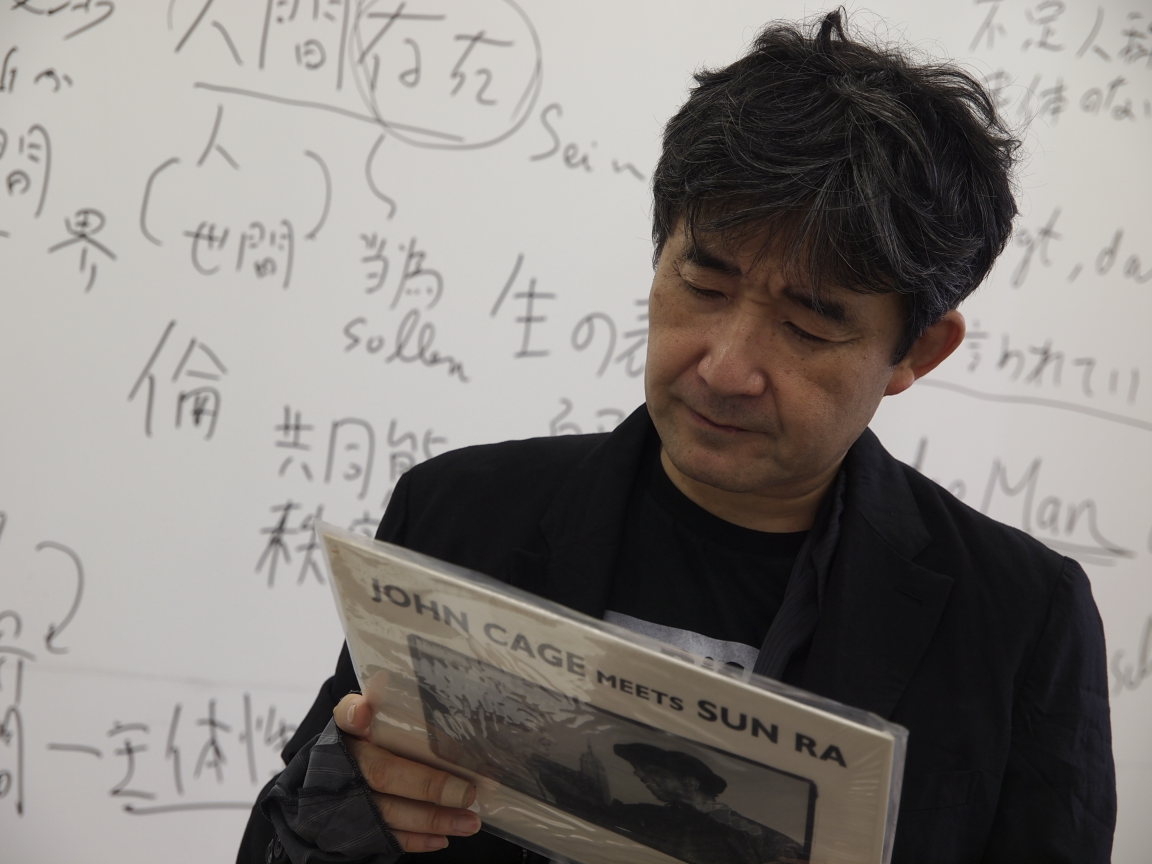
『全体主義の起原』三巻を貫くアーレントの哲学的関心の焦点は、「同一性」と「全体」の関係にあった。この場合の「同一性」とは、各人にとって「私は〇〇の一員である」と自信とプライドを持って断言できる、社会的アイデンティティのことである。
私たちは日常的に男性、日本人、〇〇県民、◇◇市民、△△社員、■■会員などのアイデンティティを使い分けているが、万事うまく行っている時は、それらを特に意識しない。戦争、長期不況、大災害などで、生活全般が危機に瀕する時、私たちは自分がどこに所属しているのか、複数の所属先の内、どれが最も頼りになるのか考えるようになる。
近代において、多くの人の主要なよりどころとなったのが、「国民国家 nation-state」である。「国民」とは、同じ言語、宗教、歴史、習慣を共有しているという自覚に基づいた文化共同体である。原則、一つの「国民」から成る「国家」が「国民国家」である。同じような生活様式や価値観を持ち、言葉が通じる同胞から構成される国家に属していれば、いざという時、守ってもらえるような気がする。
中世封建社会のヨーロッパでは、君主や貴族と、領民の間にあまり接点はないし、各地域の間の通信・交通も制限されていたので、どこに自分と同じような生き方をしている人たちがいるのかイメージしにくく、「国民」という意識は形成されにくかった。しかし、通信・交通の手段が発達し、封建的秩序が緩んで、人々が各地を移動するようになると、次第に「国民」意識が生じてくる。一七世紀の三十年戦争の結果、各国を支配する君主の主権が強化されると、君主たちも、自分がどういう「国民」を統治しているか意識するようになった。
現実のヨーロッパの諸国を見れば分かるように、一〇〇%一つの国民だけから構成される国家はないし、一つの「国民」が国境をまたいで複数の国家に居住している例は少なくない。ただ、一国民一国家に近い状態にあり、領土を拡張するか、国内にいる異分子を排除すれば、「国民国家」をほぼ達成できそうな状態にある国もあった。他の国民を追いやって、自らの「国民国家」を実現・完成しようとする試みが、ナショナリズムだ。
『全体主義の起原』の第一巻「反ユダヤ主義」は、こうした国民国家的なアイデンティティとの関係で、近代的な反ユダヤ主義が論じられている。それまでも、イエスを十字架に付けることを選択した民であり、独自の習慣を持ち、妙な仲間意識で結束していたユダヤ人に対する偏見・迫害はあったが、それは周辺地域の住民の感情的反発によるものでしかなかった。一八世紀末から一九世紀にかけて、近代的な国家機構を備えた「国民国家」が形成され、教育・文化政策、特に国語教育を通じて、「国民」意識を強化するようになると、異なった言語、宗教、慣習を持つ「ユダヤ人」という集団が目立ってくる。彼らを「国民」の中に「同化」するのか、それとも、異分子として「排除」するのかが政治的課題になってくる。
英国、フランス、ドイツでは、ユダヤ教を捨てて同化し、金融業や、法律家、医者、大学教授、ジャーナリストなど、社会的に高いステータスを獲得する人も少なくなかった。しかし、そうした一部のユダヤ人の成功と社会中枢への進出は、ユダヤ人をまだ同胞だと思っていない人たちや、努力しても社会の底辺に留まらざるを得なかった人たちの間に、羨望・嫉妬、仲間内でうまくやって、国家を乗っ取ろうとしているのではないか、という疑いを産み出すことになった。一九世紀末から二〇世紀初頭にかけて、ユダヤ系の将校を外国のスパイと簡単に認定し、有罪判決を下したドレフュス事件(フランス)や、ユダヤ人による世界征服計画を記した『シオンの議定書』が"発見"される(ロシア)といった、ユダヤ人問題を政治化する事件が相次ぐ。
第二巻『帝国主義』でも、「国民国家」が重要な役割を果たす。アフリカやアジア、中南米で植民地獲得競争を繰り広げたのは、ヨーロッパの国民国家である。植民地を獲得して、そこで得た利益を本国に還元することで、国内の階級闘争を和らげ、「国民」の「国家」への忠誠心を維持することができた。それだけにとどまらず、国内にいれば、持てあましてしまう、ならず者たち(モッブ)を植民地に送り込み、現地人を暴力的に従え、資源開発に当たらせることで、マイナス要因をプラス要因に転化することもできた。植民地獲得競争が激しくなるほど、「国民」は、ライバル関係にある隣国との闘いをより意識し、「国民国家」の繁栄を願うようになる。
加えて、ヨーロッパ人とは明らかに異なる外見をし、異質な文化・価値観を持つ現地人との接点が増えるにつれ、自分たちが、一つの「国民」に属すると同時に、ヨーロッパ人(白人)であることを意識するようになる。二重のアイデンティティ形成が進行したわけである。
自分たち白人が、世界を導く立場にいると感じるようになった、あるいは、植民地支配に対する後ろめたさを隠そうとするようになった人たちの間に、ゴビノー(一八一六-八二)やヒューストン・スチュアート・チェンバレン(一八五五-一九二七)等の「人種理論」が広く受容されるようになった。ヨーロッパ人、特にアーリア人が、人類の歴史の頂点に立っているとする考え方である。ユダヤ人の多くは外見だけからは他のヨーロッパ人と見分けるのは難しいが、チェンバレン等の理論では、アーリア人と交わり、純血性を低下させる不純因子と位置付けられた。
第三巻『全体主義』では、大衆社会化が進み、マルクス主義者の言う「階級」を含めて、人々がアイデンティティの基盤にできそうな地域・血縁共同体、同業者組合、教会・教派、身分などによる繋がりが無力化していく中で、「国民国家」がますますクローズアップされるようになった。経済危機や戦争・内乱などの例外状態が続くと、「国民国家」から異分子を排除して純化し、強化すべきという声が強まっていく。
「国家」に頼る人々は、不安定要因をなくすため、従来国家から相対的に独立していた市場を中心とする経済、文化、市民間の道徳規範なども、「国家」の管理に委ね、地域ごとの自治を廃止して、中央に一本化することを望むようになる。そうした人々の「全体」への志向に敏感に反応し、「全体」への(再)統合を掲げたのが、ナチスなどの全体主義の運動だ。ナチスの場合、「全体」とは、「国民」という西欧的な概念を超えて、ドイツ人の根源的なアイデンティティの基盤となる「民族 Volk」であり、ソ連の場合、プロレタリアートたちから構成される「人民 Volk」である。「全体主義」は、国民国家的アイデンティティに頼るようになった大衆を、「全体」への(再)統合の神話で魅了する。
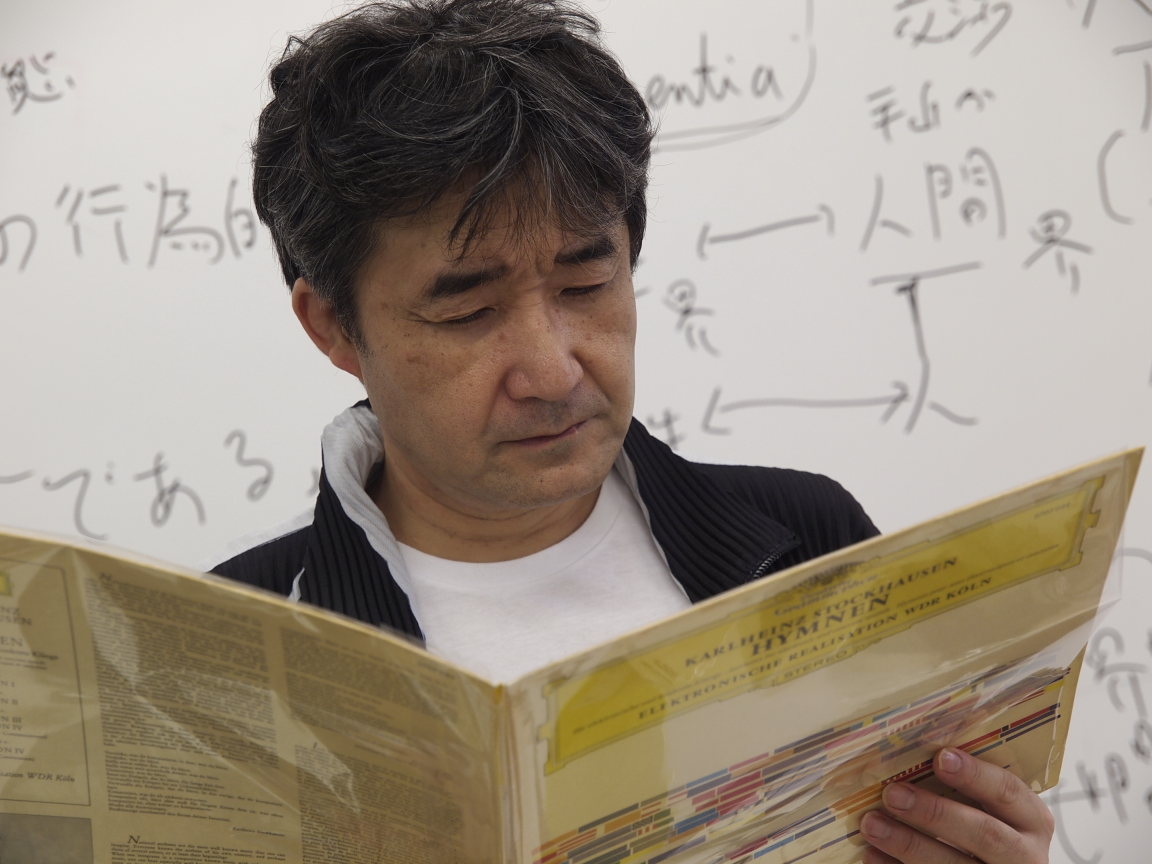 />
/>