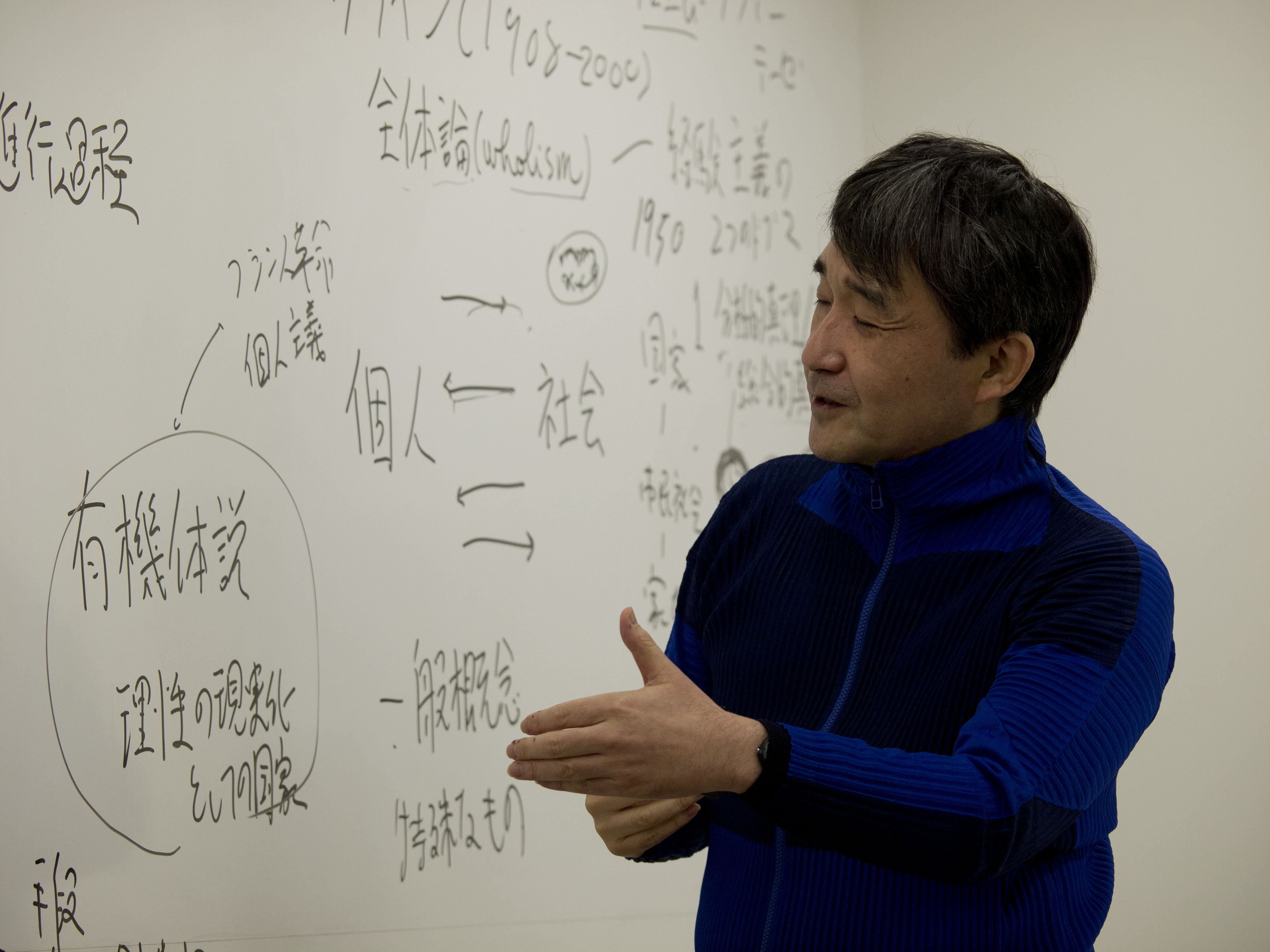第43回 アーレントとフロム 仲正昌樹
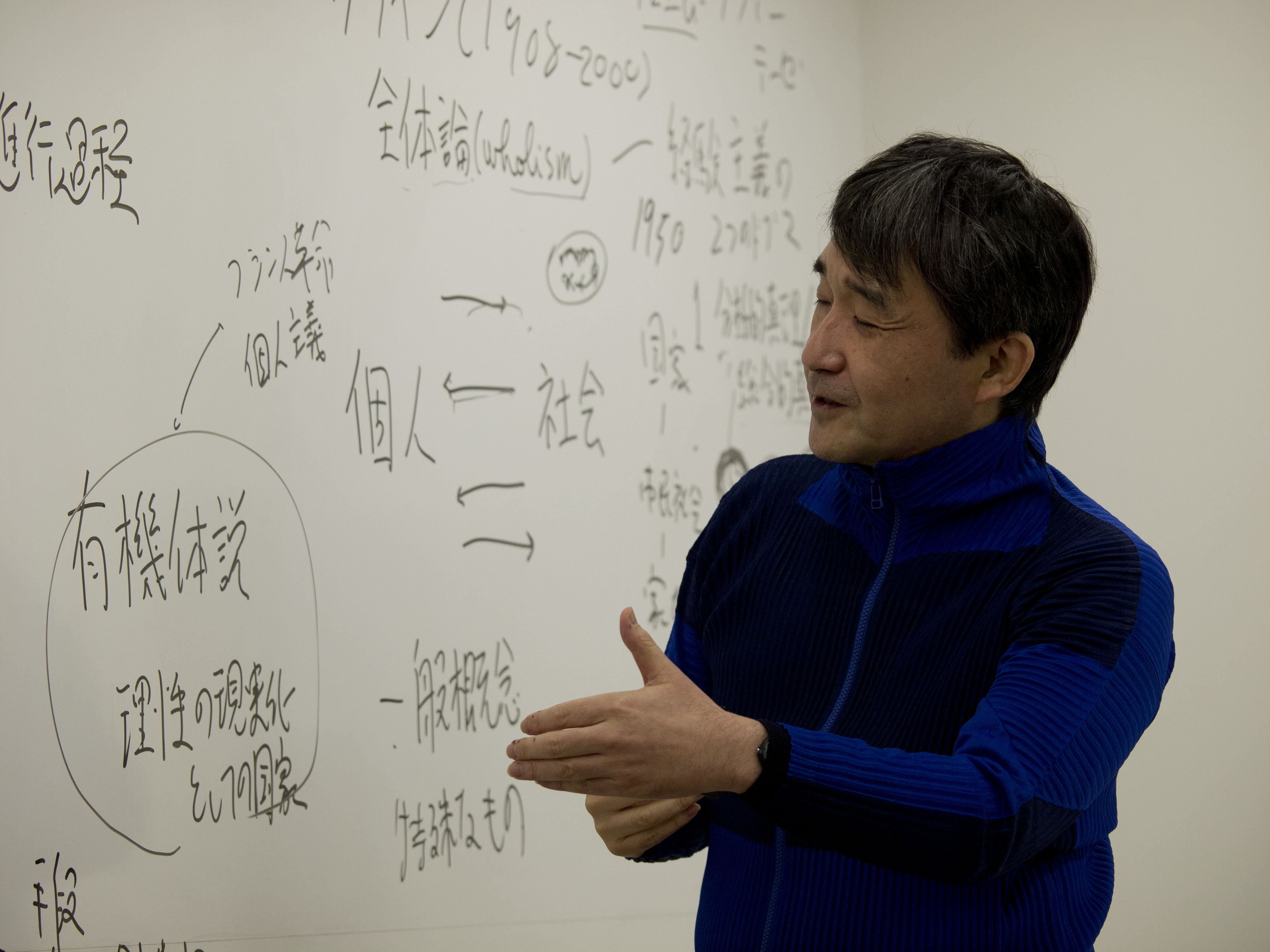
cameraworks by Takewaki
第二次世界大戦中から五〇年代にかけて、「全体主義」とは何かをめぐる多くの論考が著された。それらの中で最も影響力があり、その後の全体主義論の方向性を規定したのは、エーリッヒ・フロム(一九〇〇-八〇)の『自由からの逃走』(一九四一)と、ハンナ・アーレント(一九〇六-七五)の『全体主義の起原』(一九五一)である。
二人は同年代で、ナチスの迫害を逃れてアメリカに亡命し、定住したユダヤ系の知識人であり、フランクフルト学派と微妙な緊張関係にある、といった共通点があるが、彼らの全体主義論が対比して論じられることは意外に少ない。恐らく、両者のアプローチが違う所に焦点を当てているため、どこが共通していて、どこが違うのか判定しにくいからだろう。
社会心理学者であるフロムは、原初的な絆から解き放たれた諸個人が自らの状態(=自由)に対して抱き続ける不安が、プロテスタントの教義と結び付いた資本主義的生活様式の拡大・定着によって増幅したことに着目した。政治哲学者であるアーレントは、国民国家の枠内における――ユダヤ人など他者を排除する形での――アイデンティティの固定化と、一九世紀末から二〇世紀前半にかけての社会構造の変動(大衆社会化)と第一次世界大戦を契機としたその動揺を重視した。
大きな括りとして見ると、両者とも、西欧近代が経験した共同体感覚の喪失によって、多くの人が不透明化した世界の中で、はっきりした世界観を示し、行くべき道を示してくれる強い指導者を求めるようになり、自発的な判断を放棄し、指導者と同化していく、という構図で考えている。違いが際立つのは、フロムが、宗教が個人のアイデンティティ形成に与える影響、特にカトリックとプロテスタントのそれの違いを、自らの心理学的理論に基づいて大胆な仮説を立てて、それを宗教改革以降の歴史に当てはめているのに対し、アーレントは、独自の心理学的・社会学的な想定を前面に出すことなく、できるだけ史料に語らせる歴史家に近い手法を取っていることだろう。
ルネサンスから第二次大戦までの近代史と、個人の心理学的発達のプロセスをパラレルに描き、個性の望ましい発達の在り方について自らの見解を示すフロムの議論はポジティヴで、分かりやすい。「~からの自由」という形を取る「消極的自由 negative freedom」だけだと、他者との関係を断ち切り続けねばならないので、安定したアイデンティティを獲得できない。他者との連携によって、社会の中で自己実現する中で達成されるべき「積極的自由 positive freedom」が求められている。ただし、後者の自由に対する人々の欲求が、「全体」――「国家」「民族」「人民」「教会」等――を象徴する「権威」との合一化の欲求、すなわち、「権威」の意志を"自分自身の意志"として受け入れることによって、"自由"になろうとする欲求へと変質することにならないよう工夫しなければならない、というフロムのメッセージは、良識ある大人にとって受け入れやすい。
アーレントは、一九世紀に入る前後、フランス革命期からナポレオン戦争、復古期にかけてのヨーロッパ諸国の国民国家化のプロセスから第二次大戦までの一世紀半に絞ったうえで、この間の歴史の流れを、「反ユダヤ主義」「帝国主義」「全体主義」の三つの段階に分け、それぞれのメカニズムを構成する諸要素を細かく呈示している。近代史、法制史、経済思想史、文学史に関する一定水準以上の教養がないと、複線的に進んでいく彼女の記述について行けず、何を問題にしているのか分からなくなる。アーレント自身が念頭に置く、理想的な個人の生き方や自由な主体になるため条件が直接的に示されていない――それに相当するものは、後に『人間の条件』(一九五八)や『革命について』(一九六三)などでかなり、迂遠な形で暗示されるようになる――ので、近代史のどの段階に歪みがあったと見るべきか、テクストそれ自体からは読み取りにくい。
ドイツ人、フランス人、英国人、イタリア人...といったnation単位での国家形成や市民権の保障は、文明発展史における不可避のプロセスだったのか、それとも、全体主義への第一歩だったのか?ユダヤ人は各国民国家に同化すべきだったのか、ディアスポラの民としての独自のアイデンティティを保持すべきだったのか。アーレントは、ヨーロッパ近代史の方向性を決定した様々な出来事やプロセスが、後から振り返ってみて、極めて問題含みであったことを、史料の再構成を通じて明らかにしていくが、どれが正しい道だったか教えてくれない。きちんと読もうとする読者は混乱させられ、社会を形成しようとしながら、同時に「自由」を求める「人間」という存在自体が矛盾をはらんでいる、のではないかと思えてきて、暗い気持ちになる。
ただ、フロムのカルヴィニズム批判と、国民的アイデンティティに内在する矛盾をめぐるアーレントの議論を相互補完的な形で捉え直せば、生産的な対話ができそうにも思える。異なった社会的立場、ライフスタイル、価値観を有する人々を、教会のヒエラルキーの中で緩やかに包摂しようとしたカトリックに対し、プロテスタントは、共同体的な絆を徹底的に解体し、人々を信仰の面から自律化させようとした。特にカルヴィニズムは、各人が終末において救われるかどうかは、神以外には誰にも分からない、自分が救わる側に属していると確信したいならば、神から与えられた「使命」(だと自分が信じているもの)に徹底的にコミットし、その道で成功を収めるしかない、と説く。救われたいからこそ信じたい人間に対して、本当に救われるか最終的に分からないけれど、とにかく実践して、自分で確信しろ、というのである。理不尽だ。信仰の自由と引き換えに、こうした根源的に不安な状況に各人を追い込み、"自発的"に自らの信じるべきものを見出させようとする。信仰したくてもできない絶望の中で、自分を今すぐ救ってくれそうな「権威」にすがりつきやすいメンタリティを作り出しているようにも見える。
ほとんどの近代人がもっぱら、狭義の「信仰」をめぐる不安を抱えているというのがフロムの主張だとすると、あまりに宗教を偏重しすぎているように思えるが、神への「信仰」と限らず、自分の人生に意味、方向性を与えてくれる究極の「目的」のようなものがあることへの「信念」という広い意味に取れば、かなり説得力が増すだろう。そう考えると、アーレントの議論との接続の余地が大きくなる。
一六世紀に生まれたプロテスタントの信仰も含めて、西欧の共同体感覚を支えていた様々な信念やそれと結び付いた慣習が急速に崩壊した、啓蒙と革命の時代である一八世紀後半から一九世紀にかけて、新たなアイデンティティの基礎としてnationが浮上してきた。一つのnationに属することが、自分が価値ある存在だと確信できる基礎になったが、nationに対する"信仰"は、他のnationとの敵対関係や、ユダヤ人のように、一つのnationにまとまることが困難な人々を排除することを伴っていた。そうしたnationへの信仰が、国民国家ごとの帝国主義政策によって強化された。それが、大衆社会化の過程で再び崩れ始めたため、従来のnationを超えた、強い信仰の拠り所が求められるようになった。個人を自立化させながら、新たな信仰共同体を構成するという、(ポスト・)カルヴィニズムの自己矛盾したプロジェクトを分析したのが、アーレントだということになろう。
個人がいかなる信仰もなしにアイデンティティを確立することはそもそも可能なのか?そうやって自立した個人たちが、全体への自発的同化とははっきり異なる仕方で、繋がりを構築することはできるのか。フロムとアーレントを合わせて読むと、近代的な主体が直面する二重の課題が見えてくる。

cameraworks by Takewaki
*著者プロフィール
![]()